
親子や夫婦などの間で現金や不動産、株式などの財産を贈与する際、贈与税という税金が発生する場合があることをご存じでしょうか。
財産の贈与をするにあたっては、以下のような点を正しく理解していないと申告漏れや脱税によるペナルティを課される可能性があるため注意が必要です。
・どのような場合に贈与税が発生するのか
・贈与税の金額はどのように計算するのか
・贈与税はどのようにして申告・納税をするのか など
本記事では、贈与税の概要や贈与税が課される場合と課されない場合、贈与税額の計算方法、贈与税の納税方法などについて解説します。
- 贈与税の計算方法や税率がどのように適用されるかを知ることができる。
- 贈与税の基礎控除(年間110万円)や非課税となる特例の活用方法がわかる。
- 暦年課税や相続時精算課税など、贈与税の課税方式についての違いが理解できる。
目次
贈与税とは?

贈与税とは、個人から個人に財産を無償で与える際に受け取った側が課される税金のことです。
贈与において財産を与える側は「贈与者」、受け取る側は「受贈者」と呼ばれます。
贈与税は、1月1日~12月31日までの期間におこなわれた贈与を対象として受贈者に支払いの義務が発生するのが原則です。
贈与税の納税義務が発生した受贈者は、税務署に申告のうえ納税をおこなわなければなりません。
万が一期間内に申告および納税ができなかった場合、申告漏れ・脱税に該当して加算税や延滞税、刑事罰の対象となり得るため注意しましょう。
贈与税の課税対象になる財産には、現金に加えて株式や不動産なども含まれますが、贈与税が非課税になる特例もあるため、必ずしもすべての贈与に対して贈与税が発生するわけではありません。
贈与税と相続税の違い
簡単にいうと、財産の引き継ぎについて、所有者の生前におこなわれた際に発生するのが贈与税、所有者の死後に発生するのが相続税です。
ここでは、さらに詳しく贈与税と相続税の違いについて解説します。
1.課税対象の時期
贈与税と相続税の最も大きな違いの一つは、課税対象となる時期です。
贈与税は、生前に個人が他者へ財産を贈与した場合に課税される税金であり、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額に対して課税されます。
一方、相続税は、被相続人(亡くなった人)の死亡に伴い、その財産を相続または遺贈によって取得した場合に発生します。
つまり、贈与税は生前の財産移転に、相続税は死亡後の財産移転に適用されるという違いがあります。
なお、贈与税は毎年発生する可能性がありますが、相続税は原則として被相続人が亡くなったときに一度だけ発生するのが特徴です。
| 税の種類 | 課税対象の時期 | 発生タイミング |
|---|---|---|
| 贈与税 | 毎年1月1日~12月31日に受けた贈与 | 生前に財産を受け取ったとき |
| 相続税 | 被相続人の死亡時 | 死亡により財産を受け取ったとき |
2.課税対象となる人
贈与税と相続税では、税金を負担する対象者も異なります。
贈与税は、財産をもらった受贈者(財産を受け取る人)が支払う税金です。
贈与をおこなった側(贈与者)ではなく、受け取った側が税金を納める義務を負います。
一方、相続税は、被相続人の財産を相続または遺贈によって取得した相続人や受遺者が課税対象となります。
ただし、相続税は基礎控除があり、遺産総額が基礎控除額を超えない場合には課税されません。
また、相続税の納税義務は法定相続分とは関係なく、実際に取得した財産の割合に応じて負担することになります。
このように、贈与税は財産を受け取った個人が毎年支払い、相続税は死亡時の財産を受け取った人がまとめて支払うという点が大きな違いです。
| 税の種類 | 課税対象者 | 課税のポイント |
|---|---|---|
| 贈与税 | 受贈者(財産を受け取る人) | 贈与を受けた人が納税義務を負う |
| 相続税 | 相続人・受遺者(遺産を受け取る人) | 遺産の取得額に応じて相続税が課税される |
3.納税の時期
実際に税金を支払わなければいけない時期については、以下のように異なっています。
| 税の種類 | 納税の時期 | 申告・納付期限 |
|---|---|---|
| 贈与税 | 贈与の翌年 | 翌年の2月1日~3月15日 |
| 相続税 | 被相続人の死亡後 | 死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内 |
贈与税と相続税では、納税の時期にも明確な違いがあります。
贈与税は、財産を受け取った翌年の2月1日から3月15日までに申告・納付をおこなう必要があります。
これは、1年間に受けた贈与をまとめて計算し、翌年に税額を確定させる仕組みのためです。
一方、相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付する必要があります。
相続税の申告期限は比較的短いため、相続財産の評価や分割協議を迅速に進める必要があります。
また、贈与税は原則として一括納付ですが、相続税は一定の条件を満たせば延納や物納が認められる場合があります。
このように、贈与税と相続税では納税の時期や手続きの柔軟性に違いがある点も重要です。
贈与税の2つの課税方式と計算方法

贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。
受贈者は、どちらかを選択して納税しなければいけません。
それぞれで特徴と計算方法が異なります。
ここでは、暦年課税と相続時精算課税についてくわしく解説します。
1.暦年課税
暦年課税とは、贈与税の課税方法の一つで、1年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与額に対して贈与税を課税する制度です。
贈与税は、贈与を受けた年ごとに計算され、翌年の2月1日から3月15日までの間に申告をおこない、税金を納める必要があります。
この課税方法では、年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税は非課税となります(基礎控除)。
もし110万円を超える金額を受け取った場合、その超過分に対して贈与税が課税されます。
贈与税は、累進課税制を採用しており、贈与額が多ければ多いほど高い税率が適用されます。
税率は10%から50%まで段階的に上がり、贈与額が多くなるほど税負担が増える仕組みです。
たとえば、贈与額が200万円の場合、110万円を超える部分(90万円)に対して贈与税が課税されます。
暦年課税では、贈与者と受贈者ごとにその年の贈与額を合算して計算します。
複数回にわたって贈与を受ける場合でも、毎年の贈与額が110万円を超えるとその分に贈与税が課税されるため、贈与計画を立てて適切に控除額を活用することが重要です。
また、贈与者が亡去した場合、贈与税の課税対象となる額が相続税に影響を与えるため、贈与と相続のタイミングも考慮する必要があります。
相続時精算課税を選択していない場合、自動的に暦年課税になる点もあわせて認識しておきましょう。
暦年課税における贈与税率には「特例税率」「一般税率」の2種類があり、それぞれに税率が異なるため、その点についても解説します。
・特例税率に基づく計算方法
特例税率は、両親や祖父母から、18歳以上の子どもや孫に対して財産の贈与があった場合に適用されます。
特例税率の詳細は、以下の表のとおりです。
【特例税率における税率表】
| 基礎控除(110万円)後の課税価格 | 贈与税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
たとえば18歳以上の子どもが親から生前贈与として500万円の現金を受け取った場合、暦年課税だと特例税率が適用され、贈与税の金額は以下のように算出されます。
・基礎控除後の課税価格
:500万円(贈与財産額)-110万円(基礎控除)=390万円
・税率:15%
・控除額:10万円
・贈与税額
:390万円(課税価格)×15%(税率)-10万円(控除額)=48万5,000円
・一般税率に基づく計算方法
一般税率とは、直系尊属以外からの贈与、または直系尊属から18歳未満の子どもや孫への贈与において適用される税率のことです。
具体的には、兄弟姉妹や配偶者の父母、伯叔父母などからの財産の贈与があった場合に適用されます。
一般税率の詳細は、以下の表のとおりです。
【一般税率における税率表】
| 基礎控除(110万円)後の課税価格 | 贈与税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
たとえば、兄弟姉妹から生前贈与として500万円の現金を受け取った場合、暦年課税だと一般税率が適用され、贈与税の金額は以下のように算出されます。
・基礎控除後の課税価格
:500万円(贈与財産額)-110万円(基礎控除)=390万円
・税率:20%
・控除額:25万円
・贈与税額
:390万円(課税価格)×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円
関連記事
暦年課税とは?相続時精算課税との違いと注意点を解説【贈与税の知識】
2.相続時精算課税
相続時精算課税とは、60歳以上の直系尊属から18歳以上の子ども、または孫などに財産を贈与した場合に選択できる課税方法のことをいいます。
財産の早期移転を促進することを目的としており、贈与税の負担が軽減される点が特徴の一つです。
相続時精算課税においては、2,500万円分までの財産に対しては贈与税がかからず、その後の相続時に相続財産へ加算されて相続税が課税されます。
相続時精算課税の対象者や税率などは、以下の表のとおりです。
| 贈与者 | 贈与があった年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母など |
|---|---|
| 受贈者 | 贈与があった年の1月1日時点で18歳以上の推定相続人および子どもや孫 |
| 非課税枠 | 贈与対象者1人につき2,500万円 |
| 税率 | 一律20% |
| 計算方法 | 贈与財産の金額から特別控除(2,500万円)を引き、税率20%を乗じる |
たとえば、18歳以上の子どもが60歳以上の親から生前贈与として3,000万円の現金を受け取った場合、相続時精算課税における贈与税の金額は以下のように算出されます。
・特別控除後の課税価格
:3,000万円(贈与財産額)-2,500万円(特別控除)=500万円
・税率:20%
・贈与税額
:500万円(課税価格)×20%(税率)=100万円
なお2024年から相続時精算課税においても暦年課税と同様に年間110万円の基礎控除枠が新設されました。
上記の贈与が2024年1月1日以降に相続時精算課税においておこなわれた場合、基礎控除も加わるため、贈与税の金額が軽減されます。
・基礎控除および特別控除後の課税価格
:3,000万円(贈与財産額)-110万円(基礎控除)-2,500万円(特別控除)=390万円
・税率:20%
・贈与税額
:390万円(課税価格)×20%(税率)=78万円
関連記事
生前贈与が2,500万円まで非課税に!相続時精算課税制度とは?
贈与税の4つの特例

贈与税には、以下4つの特例があり、該当する場合は非課税や控除の対象となります。
1.基礎控除
贈与税の基礎控除とは、贈与を受けた人が一定額まで税金を免除される制度です。
具体的には、年間110万円までの贈与に贈与税がかかりません。
この基礎控除は、贈与を受けた側に適用され、贈与者(贈与をした人)の年齢や関係に関係なく、毎年の贈与額が110万円以下であれば税金を支払う必要はないというものです。
ただし、110万円を超える贈与を受けた場合、その超えた分について贈与税が課税されます。
贈与税の計算は、贈与額や受贈者との関係性、相続時精算課税などさまざまな要素によって異なりますが、基礎控除を活用することで税負担を軽減できます。
この控除は、贈与を受ける年ごとに適用されるため、毎年少しずつ贈与を受けることで、贈与税を抑える方法としても有効です。
2.住宅取得等資金の一括贈与
贈与税が非課税となる住宅取得等資金の一括贈与とは、親や祖父母から子や孫に対して、住宅購入やリフォームに必要な資金を一括で贈与する際に適用される特例です。
この特例を利用することで、一定の条件を満たす場合に贈与税が非課税となります。
非課税の対象となる金額は、贈与を受けた年の年齢や贈与の目的によって異なり、最大で1,000万円、それ以外は500万円までが非課税となります。
・省エネ等住宅:1,000万円まで
・省エネ等ではない住宅:500万円まで
主な条件としては、贈与を受けた人が住宅取得等資金を使用すること、また贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上であることが挙げられます。
さらに、住宅を取得するための契約を締結した後、一定期間内に資金を使い切る必要があります。
この特例は、贈与者が直系尊属(親や祖父母)である場合に限られるため、他の親族からの贈与には適用されません。
省エネ等住宅として認定されるためには、以下3つの基準のいずれかを満たさなければいけません。
| 基準1 | 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること |
| 基準2 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること |
| 基準3 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること |
3.教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与に関する贈与税非課税制度は、親や祖父母から子や孫に対して、教育資金を一括で贈与する際に贈与税が非課税となる特例です。
この制度を利用することで、最大1,500万円まで(2021年4月以降、受贈者が30歳未満の場合)贈与税が課税されずに教育資金を受け取ることができます。
教育資金とは、学費、学校の授業料、入学金、教材費など、教育に必要な費用を指します。
この特例を適用するための条件は、贈与者が直系尊属(親や祖父母)であり、受贈者が30歳未満であることが基本です。
また、贈与を受けた資金は、教育目的に使用される必要があり、教育資金として使わなかった分については、贈与税が課税されます。
贈与者は、贈与を受けた資金を教育機関に直接支払う方法や、指定口座に振り込む方法で贈与をおこなうことが求められます。
3.結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与は、直系尊属(祖父母や親)から18歳以上50歳未満の子や孫に対して、最大1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
この制度は、結婚や子育てにかかる費用を経済的に支援することを目的としており、贈与を受ける者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。
具体的には、結婚資金として利用できる金額は最大300万円で、残りの700万円は子育て資金に充てることができます。
対象となる費用には、結婚式の費用や新居にかかる費用、子どもの医療費や保育料などが含まれます。
この制度を利用するには、贈与契約を結び、贈与資金を専用口座に預け入れる必要があります。
贈与を受けた資金は、信託契約日以降の支払いにのみ使用可能で、贈与者が信託期間中に亡くなった場合は相続税が課税されることがあります。
関連記事
贈与税がかからない方法ってある?贈与税が非課税になる特例の内容を徹底解説
不動産や株式を贈与された場合の評価方法
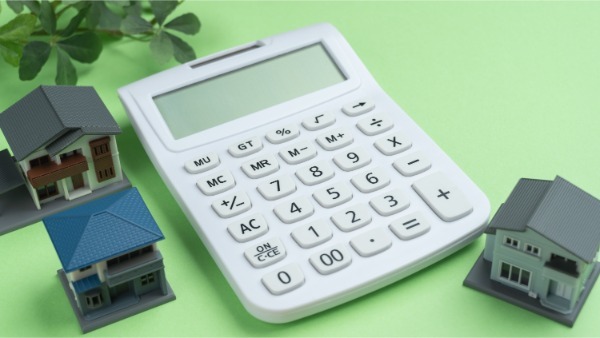
贈与税は、贈与された財産の金額を基準に計算されます。
現金は、金額が明白で変動することはありませんが、不動産や株式の場合は時期によって価値が変動します。
ここでは、不動産や株式の贈与をされた際の評価方法について解説します。
1.土地の贈与を受けた場合
土地の評価額を計算する方法には、路線価方式と倍率方式の2つがあります。
・1.路線価方式
路線価方式は、不動産の評価方法の一つで、主に相続税や贈与税の計算に使用されます。
この方式では、土地が接する道路に設定された「路線価」を基に、土地の面積を掛け算して評価額を算出します。
路線価は、標準的な宅地1平方メートルあたりの価格を示し、国税庁が公表しています。
路線価方式では、以下の計算式で土地の価格が評価されます。
計算式
・路線価方式での土地の評価額=その土地の正面路線価(円/平方メートル)×面積(平方メートル)×補正率
「補正率」とは、その土地の形状等に応じて、評価額の補正が必要な場合に用いられる数値です。
路線価は、国税庁のホームページで調べることができるため、土地の贈与を検討している場合は参照してみるといいでしょう。
・2.倍率方式
倍率方式とは、路線価が定められていない地域において用いられる土地の評価方法です。
倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じることで土地の価格を評価します。
路線価図・評価倍率表の見方は国税庁ホームページで、固定資産税評価額は都税事務所や市役所、区役所、町村役場でそれぞれに確認が可能です。
2.家屋の贈与を受けた場合
家屋(建物)の贈与においては、「固定資産税評価額」を基準に資産額の評価がおこなわれます。
固定資産税評価額とは、土地や家屋を所有しているときに課税される固定資産税などの税額の計算にも使われる評価額です。
家屋の贈与税の評価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算されるため、固定資産税評価額と同額です。
贈与対象となる家屋の固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書や市区町村が保有する固定資産課税台帳で確認できます。
関連記事
不動産の相続にはどんな税金がかかる?税額の計算方法も解説!
3.上場株式の贈与を受けた場合
上場株式の贈与税評価においては、贈与される株式数に以下4つのなかで最も低い金額を乗じて評価額を計算します。
・贈与日時点での最終価格
・贈与月における毎日の最終価格の平均額
・贈与月における前月の毎日の最終価額平均額
・贈与月における前々月の毎日の最終価額平均額
4.非上場株式の贈与を受けた場合
非上場株式の場合、上場株式のように市場でオープンに価格が付けられて売買されるものではないため、その評価方法は上場株式の評価よりも複雑です。
非上場株式を評価する際は、その株式を発行している会社を以下の流れで分類し、それぞれのカテゴリーに応じた評価方法で評価額が計算されます。
・ステップ1.株主による区分
贈与により新たにその会社の株主になる人が、その会社の経営支配力を持っている「同族株主等か」、そうではない「少数株主等か」によって、まず2つに区分されます。
・ステップ2.会社種類による区分
上記「同族株主等」は、その会社が開業後3年未満の会社である場合や、清算中の会社である場合などの「特定の評価会社」に該当するか、それ以外の「一般の評価会社か」によって、さらに2つに区分されます。
・ステップ3.会社規模等による区分
上記「特定の評価会社」に該当しない、「一般の評価会社」は、会社規模(従業員数や総資産価額、取引金額等)によって、さらに3つに区分されます。
以上3つのステップ区分により会社を分類し、それぞれのカテゴリーに応じた評価方法で評価額が計算されます。
土地を贈与する際に節税する方法
土地を贈与する際、家建付地として贈与することで評価額を下げることができます。
「貸家建付地」とは、賃貸物件(貸家や賃貸アパートなど)が建てられている土地のことです。
貸家建付地には、第三者が使う建物が建てられており、所有者自身が自由に使えないと解されるため、土地の評価額が安くなります。
贈与する土地に賃貸物件を建てて貸家建付地にすれば、使用に制限のない土地として贈与する場合よりも贈与時の評価額を下げることができ節税効果が見込めるということです。
貸家建付地の評価額は、以下の計算式で求めることができます。
・自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
借地権割合は、国税庁のホームページで参照ができるため、確認しておきましょう。
贈与税が課される事例と課されない事例
贈与税は、個人から個人に財産を無償で与える際に一定の条件を満たすことで発生する税金です。
しかし具体的にどのような場合に課税されるのでしょうか?
ここでは、贈与税が課される場合と課されない場合について、具体的な事例を用いて解説します。
贈与税が課される7個の事例
贈与税が課されるのは、以下7個のような事例の場合です。
事例1
:個人が年間110万円を超える金額の財産を受け取った
事例2
:掛金負担者以外が生命保険または損害保険の満期保険金を受け取った
事例3
:時価の相場よりも低い金額で財産を親族から受け取った
事例4
:親族から借金返済などの免除を受けた
事例5
:不動産を取得した際、実際の資金負担と異なる割合で持分登記をした
事例6
:客観的に返済不可能な額の金銭を無利息・無催告・ある時払いで借りた
事例7
:その他経済的な利益など、贈与とみなされる行為があった
贈与税においては、年間110万円分の非課税枠があるため、その範囲内であれば課税対象にはならず、それを超える金額が課税対象となります(事例1)。
現金や不動産、株式などの財産の贈与がなかった場合でも、自らが保険料を負担していない保険の保険金を受け取ったり借金の返済免除を受けたりした場合は、実質的な財産の贈与とみなされて贈与税を課される場合があります(事例2~7)。
なお、夫婦で購入した住宅においては、以下のような場合、贈与税の課税対象になり得るため注意が必要です(事例5)。
夫名義で組んだ住宅ローンの頭金の支払いや返済を妻の収入から行うおこなう
夫名義で住宅ローンを組んだ自宅を夫婦の共同名義で登記する
夫婦共同で組んだペアローンを夫の単独名義の住宅ローンに借り換える など
贈与税が課されない10個の事例
贈与税が課されないのは、以下10個のような事例の場合です。
事例1
:法人から財産の贈与を受けた
事例2
:選挙候補者が金品を受け取った
事例3
:奨学金を支給するために特定公益信託を受け取った
事例4
:生活資金など、親から一般的な金銭を受け取った
事例5
:見舞金や香典、贈答などを受け取った
事例6
:金融機関から教育資金の一括贈与を受け取った
事例7
:金融機関から子育て資金などの一括贈与を受け取った
事例8
:公益目的の事業者からその目的の範囲内で財産を受け取った
事例9
:心身障害者扶養共済制度に基づく給付金を受け取った
事例10
:贈与者の死亡から7年以内に財産を受け取った
贈与税は、個人と個人の間で引き継がれた財産を対象としているため、法人との間で引き継がれた財産に対しては贈与税ではなく法人税や所得税が課税されます(事例1)。
財産の贈与があった場合でも、生活資金や見舞金などの名目であったり、教育や子育てに充てることが目的であったり、公益目的であったりする場合は贈与税の課税対象にはなりません(事例3~9)。
贈与者の死亡から7年以内に、故人から財産の贈与を受けていた場合、贈与された財産を相続財産に加算して相続税の課税対象とする「生前贈与加算」という制度があります。(事例10)。
生前贈与加算は、故人の死亡日から遡って7年間において贈与された財産について、相続したものとして、贈与税ではなく相続税の課税対象とする制度です。
なお生前贈与加算の対象期間は、2023年まで3年以内でしたが、2022年12月に発表された「与党税制改正大綱」により2024年から7年間に延長されました。
贈与税の4つの納税方法
贈与税の納税方法には、以下の4つがあります。
1.ダイレクト納付で納税
e-Taxを使ってインターネット上で申告書を提出し、預貯金口座からの引き落としによって納税することができます。
なお事前に専用の届出書をe-Taxで提出することが必要です。
利用できるまでには、届出書提出から約1ヵ月かかるので注意しましょう。
参考サイト:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
2.インターネットバンキングで納税
インターネットバンキングに対応している金融機関を利用し、電子納付することも可能です。
3.クレジットカードで納税
「国税クレジットカードお支払サイト」というサイトを活用することで、クレジットカードで贈与税を納税することもできます。
クレジットカードでの納税の場合、納税額に応じて決済手数料がかかるため、覚えておくといいでしょう。
4.コンビニで納税
国税庁のホームページ上でQRコードを作成し、コンビニのレジで贈与税を納税することもできます。
こちらの方法の場合、30万円以上の納税はできないため、注意が必要です。
まとめ|特例も活用して賢い贈与を

贈与税の特例を上手に活用することは、税負担を軽減し、効率的な財産移転を実現するために重要です。
基礎控除や各種特例をうまく利用することで、贈与を受ける側にかかる税金を抑えることができます。
特に、教育資金や住宅取得資金の贈与などには非課税の制度が設けられており、賢く利用すれば大きな税負担の軽減が可能です。
贈与のタイミングや方法をしっかりと計画し、特例を活用することで、財産を次世代へ円滑に移すことができるでしょう。
関連記事
家族間の贈与税はどうなる?税金がかかるケースとかからないケース





